「こどもも成長して手も離れてきたし、2人目が欲しいけどなかなかできない。1人目は自然に授かったのに……」
仕事や家事・育児に追われる日々のなかで「第二子不妊」に悩むご夫婦は決して少なくありません。
じつは、2人目をなかなか授からないのには出産を経た体の変化や加齢による卵子の質の低下、夫婦の生活リズムの違いなど、さまざまな要因が関係しています。
それなのに、周りからは「2人目はまだ?」「一人っ子はかわいそう」と言われてプレッシャーを感じたり、1人目との年齢差が開いていくことに焦りを感じたりする方も多いのではないでしょうか。
 Webライター
Webライター水野 真里さん
この記事では、看護師であり自身も不妊治療の経験のある筆者が、仕事をしながら2人目の不妊治療に臨む女性に向けて、不妊となる原因や治療の流れ、仕事と不妊治療の両立の工夫をわかりやすく解説します。
第二子不妊が起こる主な原因


不妊症とは「妊娠を望んでいる健康な男女が避妊せずに夫婦生活を営んでいるのに、1年たっても妊娠しない状態」を言います。[1]そのなかでも、第二子不妊にはさまざまな要因が関係しています。体質や生活習慣だけでなく、ライフステージの変化も大きく関係しているのです。



水野 真里さん
なかでも結婚や出産の年齢が上昇していることは、第二子不妊の重要な背景のひとつです。
結婚や出産年齢の上昇
厚生労働省の人口動態統計によると、初婚年齢は1985年には男性28.2歳、女性25.5歳でしたが、2022年には男性31.1歳、女性29.7歳となっています。[2]また、第一子出生時の母の平均年齢は、1985年は26.7歳でしたが、2024年には31歳となっています。[3]



水野 真里さん
女性が生涯のうち排卵できる数は400〜500個ほどしかありません。[1]
結婚や出産をする年齢が上がると残りの卵子が減り、質の低下も起きやすくなり、第二子の妊娠が難しくなる場合があります。[4]
出産による体の変化
第一子を帝王切開で出産した場合、当時の傷跡が第二子不妊の原因となる場合があります。これを帝王切開子宮瘢痕(はんこん)症と呼びます。
帝王切開子宮瘢痕症の症状は、生理が長引く、月経困難症、おりものの異常、不妊などです。



水野 真里さん
第二子不妊の原因が帝王切開子宮瘢痕症の場合、適切な治療をすれば第二子を妊娠する可能性が上がります。[5]
育児と仕事による生活リズムの変化
第一子を出産後、授乳や夜泣き対応、復職などで生活リズムは大きく変わったのではないでしょうか。生活リズムの変化により、人はストレスを感じます。ストレスはホルモンバランスの乱れにつながり、排卵や着床に影響を及ぼす可能性があります。[6][7]



水野 真里さん
また、夫婦の時間が減るためスキンシップ自体が減る場合もあるでしょう。
夫婦関係の変化
こどもが生まれてから関係が悪化する夫婦は少なくありません。
妻は出産を経て母親になるとこども優先になり、夫にも「父親として一緒に育児に参加してほしい」と期待します。一方で、夫はこどもが生まれる前のライフスタイルを崩したくないと思うことが多いのです。



水野 真里さん
このためすれ違いが起き、家事と育児に関する埋められない夫婦の溝が明らかになり、関係性が危機的状況におちいる夫婦は決して少なくないでしょう。[8]
夫婦の関係性が悪化するとスキンシップは減少するため、第二子不妊につながる一因になると考えられます。
不妊治療をはじめるタイミング


不妊治療をはじめるタイミングについて悩む人は多いと思います。ですが、はじめたいと思ったときが不妊治療をスタートさせるタイミングです。



水野 真里さん
年齢が若いほうが妊娠率は高いので、悩んで時間だけ過ぎてしまうよりは、まずは自分だけでもクリニックに足を運んでみるのもいいでしょう。
もちろん、夫婦で足並みをそろえて治療をはじめられるのがベストです。
不妊治療をはじめる前にできること


不妊治療をはじめる前に、自分でできる準備があります。不妊治療をはじめてから並行して準備することも可能ですが、もし時間に余裕があるなら、先に取り組んでおくことで治療がスムーズになり、心身の負担を減らすことにもつながります。



水野 真里さん
たとえば、生活習慣の見直しや基礎体温や生理周期の把握、夫との話し合いなど、前もってできることはたくさんあります。
生理周期や基礎体温を記録する
生理周期や基礎体温は、不妊治療時の検査や治療方針を決める際に必要な大切なデータです。受診時に正確な情報を伝えることで、医師も排卵があるかどうかを確認し、妊娠しやすい時期を把握できます。



水野 真里さん
必ずなくてはならないわけではありませんが、一般的には最低でも数ヶ月分の生理周期と基礎体温の記録が必要とされています。
生活習慣の見直し
不妊治療をはじめるにあたり、女性だけでなく夫婦ふたりで運動や食事、睡眠や喫煙などの生活習慣を見直すことが重要です。なぜなら、不妊の原因は女性側だけにあるのではなく、約半数は男性側にあるためです。



水野 真里さん
男性も肥満や喫煙、睡眠不足、ストレスなどにより、精子の数の減少や、運動率が低下する可能性があります。[9]
夫婦での話し合い
不妊治療は通院の回数や費用、心身の負担が大きいためあらかじめ夫婦で治療にかける時間や費用、今後のライフプランなどを話し合っておきましょう。治療中のストレスを減らし、夫婦ふたりでの協力体制を整えやすくなります。



水野 真里さん
多くの不妊治療クリニックでは、夫婦向けの説明会を開催しているので、ふたりで説明会に足を運んでみましょう。
不妊治療の検査・流れ・費用について


不妊治療をはじめる前は、どんな検査や治療があるのか、そしてどのくらい費用がかかるのか不安に感じる方も多いと思います。不妊治療の検査では、まず不妊の原因を調べるところからはじまります。検査の内容や、段階的に進んでいく治療の流れについても理解しておくことで、安心して自分に合った治療を選べるでしょう。
どんな検査をする?
女性の検査は、生理周期にあわせて複数回、血液中のホルモン濃度をはかる血液検査、超音波検査、子宮卵管造影検査などを行います。男性が関わる検査は血液検査や精液検査、フーナーテスト*です。この一連の検査をするために、まずは4~5回の通院が必要とされています。[10]



水野 真里さん
必要に応じて子宮鏡検査や、腹腔鏡での検査や手術が行われることもあります。
不妊治療のステップ
検査が終わると、年齢や自然妊娠の希望にもよりますが、一般的に次の順番でステップアップしていきます。
①タイミング法:排卵日を推測して排卵前に性行為する方法。
②人工授精(AIH):パートナーの精子を人工的に子宮に注入する方法。
③体外受精(IVF):採卵した卵子に精子をかけて自然に受精させ、子宮内に戻す方法。
④顕微授精(ICSI):採卵した卵子に、精子を直接注入する方法[10]
なお、不妊の原因がはっきりしている場合は、まずその治療を行ってから不妊治療に進むケースもあります。
不妊治療の費用について
不妊治療の費用は、2022年から保険適用となっています。一般不妊治療(タイミング法や人工授精など)だけでなく、高度不妊治療(体外受精や顕微授精など)についても保険が適用されます。保険適用となる前は自費診療だったため、高度不妊治療は高額となり、筆者も経済的な面で大きな負担を感じていました。



水野 真里さん
年齢や回数に条件はありますが、不妊治療が保険適用となったことで患者さんの金銭的・精神的負担は少し軽くなったと言えるかもしれません。[11]
第二子不妊治療と仕事を両立するために


第二子不妊治療と仕事を両立するうえで大切なのは、夫をはじめとした周りのサポートです。なぜなら、第一子の年齢にもよりますが、不妊治療と子育てと家事を並行して行うのは、ひとりでは難しいからです。



水野 真里さん
不妊治療の病院では、第一子不妊の患者さんへの配慮から、子連れ不可となっているところもあります。
この場合、通院の間は誰かに第一子の世話をしてもらうことが必要になります。
上司に不妊治療中であることを報告
不妊治療していることを上司に伝えるのは抵抗がある方もいると思いますが、スムーズに治療をすすめるためには報告しておくと安心です。筆者も抵抗がありましたが、夫にすすめられ、上司に相談してから不妊治療をはじめました。



水野 真里さん
時間指定のない検査の日は仕事終わりに通院していましたが、どうしても休む必要があったときの連絡もスムーズに行えたので、結果的には上司に伝えて良かったと思っています。
通院のために使える制度
不妊治療している方と会社との円滑なコミュニケーションのために作られた「不妊治療連絡カード」という厚生労働省のツールがあります。



水野 真里さん
不妊治療を受ける方が、主治医からの診察に基づき、治療や検査のための通院などに必要な配慮について会社の人事労務担当者に伝えるためのものです。[12]
また、企業によっては不妊治療のための休暇を定めているところもあります。
メンタルケア
筆者は第一子を授かるまで約1年半かかりましたが、不妊治療は「出口の見えないトンネル」のようだと感じました。受精卵を移植し期待しても治療の成果が出ないことが続き、徐々に疲弊していきました。燃え尽きないためにも、自分だけで頑張りすぎないことが大切です。



水野 真里さん
夫に相談したり、通院している病院でのカウンセリングを利用するなど、周りのサポートを受けながら続けていきましょう。
バランスを取りつつ不妊治療に臨もう


不妊治療と仕事の両立には、夫をはじめとした周囲のサポートが大切です。規則正しい生活を心がけながら、ストレスをためずに不妊治療に向き合っていくことが、妊娠への第一歩となります。



水野 真里さん
職場で不妊治療の通院に使える制度があればぜひ活用しましょう。
不妊治療をはじめたいと思ったら、早めに専門医へ相談されることをおすすめします。
[1]こども家庭庁>不妊のこと DICTIONARY>妊娠・不妊の基礎知識
[3]厚生労働省>統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 人口動態調査 > 結果の概要 > 令和6年(2024)人口動態統計月報年計(概数)の概況
[4]秋田大学大学院医学系研究科医学専攻 機能展開医学系 産婦人科学講座>研究者募集>寺田教授の研究>加齢による卵子の質低下の本質解明の解明
[5]滋賀医科大学産科学婦人科学講座>診療案内>帝王切開子宮瘢痕症(CSDi)外来
[6]徳島生殖医療研究室>不妊治療と生殖補助医療>3 不妊症の原因と転帰 ~原因疾患、卵管因子、子宮因子~
[7]下屋 浩一郎,勝山 博信.妊娠中の母体ストレスおよび着床との関連に関する検討,総合分担研究報告,2010,17.p169.p170
[8]三田村 仰,新舎 純子,原田 梓,安田 裕子.親への移行期に妻側が体験する夫婦関係が危機に至るプロセス,日本心理学会大会発表論文集,2022,86,p830
[9]こども家庭庁>不妊のこと DICTIONARY>男性不妊について
[10]こども家庭庁>専門家へのインタビュー>不妊治療って何をするの?検査やステップを専門医が解説
[11]こども家庭庁>政策>母子保健・不妊症・不育症など>不妊治療に関する取組
[12]厚生労働省>政策について>分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 雇用均等>パンフレット、関連資料、調査結果>パンフレット>不妊治療と仕事との両立について>不妊治療連絡カード


Webライター:水野 真里さん
看護師歴10年以上。総合病院やクリニックにて内科や整形外科などを経験し、企業看護師としても勤務していた。また、不妊治療を経て1人のこどもの母親として子育て奮闘中。妊娠出産のブランクを経て現在皮膚科クリニックにて勤務しながら、Webライターとして活動中。読者の気持ちによりそい、悩みを解決できるような文章を目指しています。
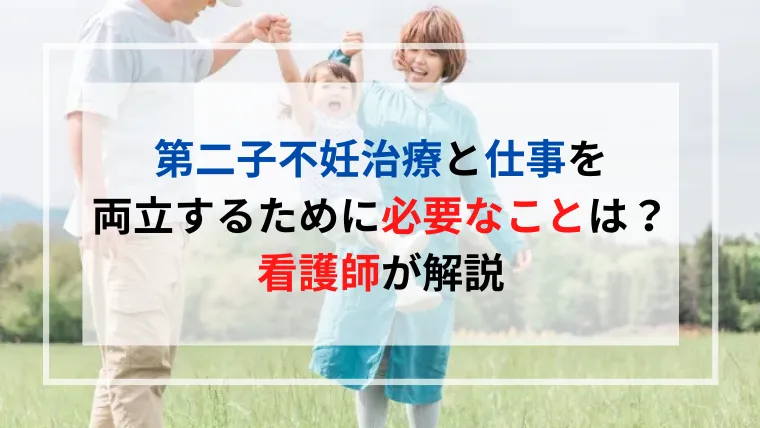
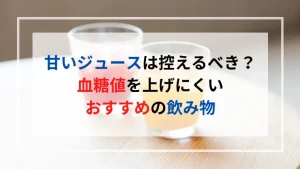
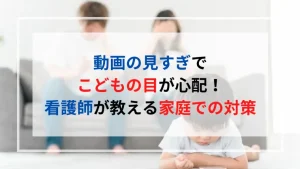
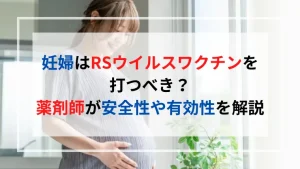
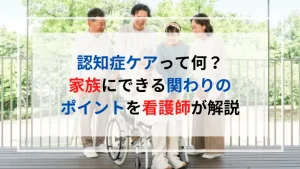
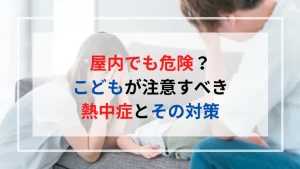
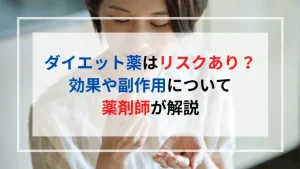
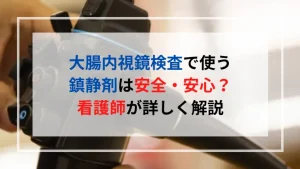
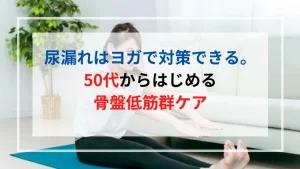
コメント