5人に1人が認知症になると言われている中、家族や身近な人が認知症を発症し悩んでいる方も多いと思います。発症してしまったら最後。家族のことも忘れ去られてしまう、何もかも介護が必要になり目が離せない……など、認知症にマイナスなイメージを持つ人もいるでしょう。
筆者はこれまで精神科・認知症グループホームで看護師として認知症の方々と関わってきました。
 看護師ライター
看護師ライター山下 なつさん
これまでの経験から、関わり方や周りの環境次第で「その人らしく」生活を続けることは可能であると実感してきました。
この記事では看護師の筆者が認知症の基礎知識や具体的な関わり方のポイントを分かりやすく解説します。
認知症を理解する


「認知症」とは、様々な病気により、脳の神経細胞の働きが徐々に変化し、認知機能(記憶、判断力など)が低下して、社会生活に支障を来した状態をいいます。
代表的な認知症として以下があげられます。[2]
| 種類 | 原因として考えられること | 特徴 |
| アルツハイマー型認知症 | アミロイドβというタンパク質が脳に溜まり、脳が萎縮する。 | 昔のことは覚えているが新しいことは覚えてられない。症状は徐々に進行する。 |
| 血管性認知症 | 脳出血や脳梗塞などの脳血管障害。 | 脳血管障害が起こるたびに症状は進行する。障害部位により症状が違う。 |
| レビー小体型認知症 | レビー小体というタンパク質が脳内に溜まる。 | 現実には見えないものが見える幻視や、手足が震えたり筋肉が固くなる症状がみられる。 |
| 前頭側頭型認知症 | 脳の前頭葉・側頭葉で脳が委縮する病気。 | 感情の抑制が効かなくなったり、社会のルールを守れなくなったりするため、性格が変わったように見えることもある。 |
治療は認知症の種類、症状によって異なり、薬物療法と非薬物療法を組み合わせて行います。
薬物療法:原因となる病気の治療と、進行を緩やかにするための治療。
非薬物療法:認知機能の改善を目指すリハビリテーション、過去の記憶を思い出す回想法など。



山下 なつさん
認知症は完治を目指すことは困難です。しかし家族や周囲の方のケアで症状の進行を緩やかにできます。
基本的なケアの5つのポイント


認知症の人にとっては、接し方自体が状態の安定や向上に向けた重要なケアとなります。[3]
認知症になったからといって、全てのことができなくなるわけではありません。
今までの生活を維持できる姿を見れば、家族も安心できますよね。
そのためには当事者を主体とした関わりが大切です。



山下 なつさん
不安や混乱を減らし、症状の進行を抑えるための関わり方のポイントを解説します。
先回りせず、見守る
なんでも先回りしてやってしまうことは、できることまで奪ってしまうことになり、自尊心を傷つけてしまいます。



山下 なつさん
認知症の方はペースを乱されると興奮・混乱してしまうため、ゆったりとした気持ちで見守りましょう。[3]
叱らない・否定しない
症状により失敗も増えてきます。現実を突きつけ叱ってしまうと自尊心を傷つけ、負の感情が残ってしまいます。
その結果、うつ状態や無気力、暴力・暴言などの症状が悪化する場合も。



山下 なつさん
冷静に本人の声にしっかり耳を傾け、尊重する関わりを心がけましょう。[3]
簡潔に、分かりやすく伝える
認知機能の低下により、理解力も今まで通りとはいきません。
一度にたくさんのことを話すと混乱してしまいます。
顔を見ながら相手のペースに合わせ、簡単な言葉で短く伝えるのがいいでしょう。



山下 なつさん
言葉だけでは伝わりにくいため、身振り手振りを交え、表情が見えるように会話しましょう。[3]
環境の変化は最小限に
「いつもと同じ」でないと不安になってしまうため、安心できる環境づくりが大切です。
急激な環境の変化は混乱や不安を生じ、ストレスから症状悪化のリスクも考えられます。



山下 なつさん
周りの環境が変化する場合は、少しずつ慣らすことも必要です。[3]
理解する・共感する
できないことが増えることでネガティブな気持ちになりやすく、疎外感を感じやすくなります。つじつまが合わない言動だとしても、共感し受け止めることで安心し気持ちが落ち着きます。



山下 なつさん
スキンシップによる触れ合いも心の安定に有効です。[3]
こんな時どうする?症状別対応例


認知症の方によく見られる、困った症状と対応を紹介します。[4]
認知症は進行していく病気ですが、全ての人に同じように症状が出るわけではありません。大切なことは、今目の前にいるその人を見ることです。周囲からみたらよく分からない症状に見えても、本人は自分なりの考えのもと行動しています。



山下 なつさん
過度に不安にならず認知症当事者が安心して過ごせる、居場所を作りましょう。
同じことを何度も聞く・繰り返す(記憶障害)
ご飯を食べたことを忘れたり、同じことを何度も話したりすることは認知症の症状によるもので、本人に悪気はありません。
「忘れる」という特性を利用した接し方も効果的です。
✖「ご飯はもう食べたでしょ」「同じこと何回言わせるの」
〇「今準備しているから待ってて」→待っているうちに忘れてしまう。
本当に空腹であれば軽食を提供し待ってもらう。
うろうろ歩き回る
理由なく歩き回っているように見えるかもしれません。トイレに行きたいのに場所が分からない、探し物をしている、不安で落ち着かない……



山下 なつさん
困っていることはないか、理由を探ってみましょう。
自宅から外に出てしまう場合は、持ち物に名前を付け近隣の交番や施設と情報共有するなど事前の対策も大切です。
✖「どこ行くの?危ないから座ってて」
出ていけないように閉じ込めるのはNG。
〇「何か探しもの?一緒に探しましょうか」
被害妄想
「泥棒がいる、盗まれた」「命を狙われているんだ」といった、実際には起きていないことも、本人にとっては現実なのです。



山下 なつさん
否定せず、困っている気持ちを受け止めましょう。
探し物を一緒にする際は、本人が見つけられるようにさりげなくサポートしましょう。
先に見つけてしまうと、隠し持っていたと疑われてしまうこともあります。
✖「そんなわけないでしょ」
〇「それは困ったね。一緒に探そう」
「怖い思いをしたね、見回りしてくるから安全なところにいてね」
暴力
認知症になってから怒りっぽくなったり、感情を抑えられずに暴言・暴力が見られたりすることもあります。



山下 なつさん
距離をおいて見守ることも必要です。
排泄トラブル
失禁や、失敗したことを隠す行為も症状の一つです。
トイレの場所は分かりやすく目立つように表示しましょう。



山下 なつさん
羞恥心は残っているため、さりげなくトイレへ案内し、失敗したときは決して責めずにフォローしましょう。
認知症とともに暮らすためにできること


認知症当事者も、支える家族も「助けて」といえる関係を築くことが大切です。不安や困りごとは家族だけで抱え込まず、地域包括支援センターへ相談してみましょう。
認知症の状態に応じたサービスの流れをまとめた「認知症ケアパス」が各市町村にあります。[5]



山下 なつさん
さまざまなサービスを利用し、本人も介護者も穏やかに過ごすことを目指しましょう。
認知症コミュニティ
認知症の人や家族が情報交換をしたり、日頃の悩みを分かち合えたりする交流の場があります。
在宅サービス
住み慣れた自宅で生活を続けるため、介護サービスを受けられます。
施設サービス
専門スタッフのサポートを受けながら生活します。
そのほか、施設に通うデイサービス(通所介護)もあります。[15]
認知症ケアを知って、自分のことも大切に


関わり方の工夫で認知症の方に大きな安心感を与え、困っている症状の軽減につながります。
認知症になっても喜びや悲しみ、怒りなどの感情はしっかりと残っています。



山下 なつさん
穏やかな時間を一緒に過ごす、家族の笑顔が一番の認知症ケアではないでしょうか。
体も心も疲れてしまう前に、専門機関やサービスを利用し一人で抱え込まないようにしましょう。
【引用】
[1]政府広報オンライン> 健康・医療・福祉>福祉・介護>知っておきたい認知症の基本
【参照】
[2]国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所>こころの情報サイト>こころの病気を知る-認知症
[4]2023年,株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン,佐藤眞一,認知症心理学の専門家が教える 認知症の人にラクに伝わる言いかえフレーズ,p98.110.114.116.118.156
[6]厚生労働省>政策について>分野別の政策一覧>福祉・介護>介護・高齢者福祉>認知症施策>主な認知症施策>認知症カフェ
[8]厚生労働省>介護事業者・生活関連情報検索>公表されているサービスについて>どんなサービスがあるの?‐訪問介護(ホームヘルプ)
[9]厚生労働省>介護事業者・生活関連情報検索>公表されているサービスについて>どんなサービスがあるの?‐訪問入浴介護
[10]厚生労働省>介護事業者・生活関連情報検索>公表されているサービスについて>どんなサービスがあるの?‐訪問リハビリテーション
[11]厚生労働省>介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)について
[13]厚生労働省>有料老人ホームの概要
[15]厚生労働省>介護事業者・生活関連情報検索>公表されているサービスについて>どんなサービスがあるの?‐通所介護(デイサービス)


看護師ライター:山下 なつさん
精神科、派遣看護師を経て現在は高齢者施設で看護・介護業務を担う。
育児に奮闘しながら転勤族の暮らしを楽しみ、看護師×ライターに挑戦中。
趣味は旅行、読書。
「寄り添うことば」をモットーに、経験をいかした分かりやすい文章をお届けします。
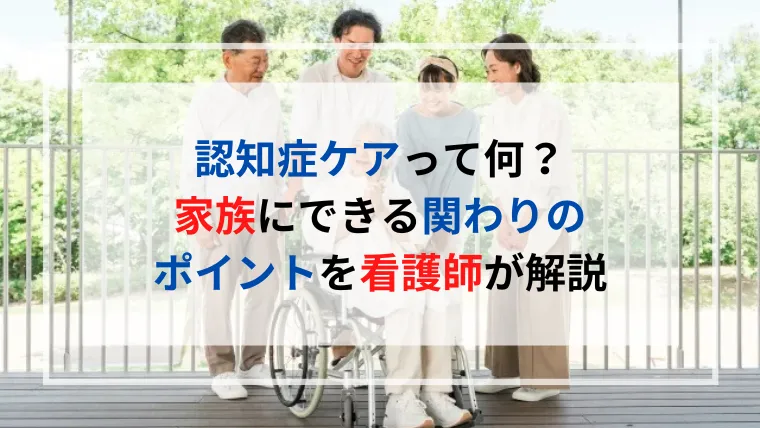
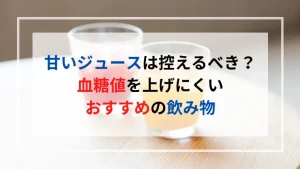
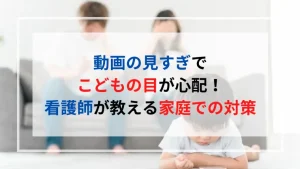
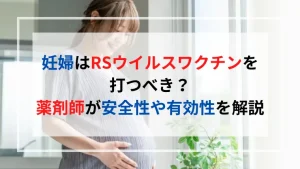
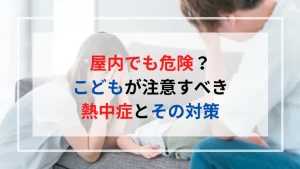
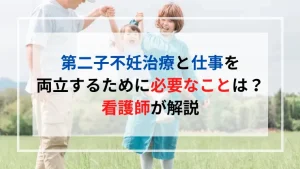
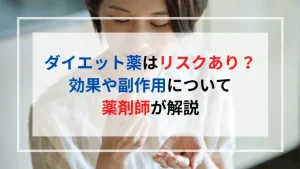
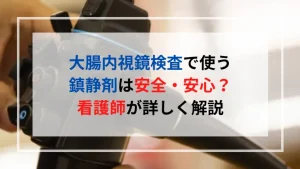
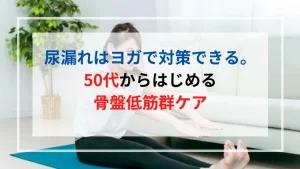
コメント