第16回出生動向基本調査(2021年)では、第一子出産後に仕事を続ける女性は5年前に比べて増加し、約7割と報告されています。[1]その中の約8割が育児休業制度を利用しています。[1]出産後も働くことを選択し、育児休暇後に復職する人が増えている状況は、多くの女性が活躍する看護師にも当てはまるでしょう。
一方で、職場復帰を考えている方は「子育てしながら今までのように働けるかな」と不安が大きいかもしれません。すでに職場復帰されている方は「職場でも帰宅後も慌ただしくて時間の余裕がない」と、悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、仕事と子育てを両立したい方に、育児中に利用できる制度や両立のコツについてご紹介します。
 看護師ライター
看護師ライター高瀬 あやさん
現役ママ看護師の筆者や周囲のママ看護師によくある悩みや経験談もお伝えしていますので、参考にしてみてください。
子育て中の看護師によくある悩み


看護師という職業は命に関わる仕事であり、責任が重く、勤務時間も不規則になりがちですよね。とくに子育て中は、夜勤が難しく希望どおりに働けないうえ、こどもの体調不良による急な欠勤も避けられません。さらに、育児・家事・仕事に追われ、肉体的にも精神的にも負担を感じている方もいるのではないでしょうか。



高瀬 あやさん
筆者や周囲のママ看護師からよく聞く悩みをご紹介します。
夜勤ができない
家庭の事情により、夫が夜勤や遅い帰宅となるため、自身の夜勤は難しいという声は筆者の周囲でも聞かれます。一方で、夜勤を避けることで収入が減る不安や、職場での立場に影響が及ぶことを心配する方もいます。
こどもの体調不良で欠勤が多い
保育園児は体調を崩しやすく、急な呼び出しや欠勤が重なることも少なくありません。職場に迷惑をかけてしまうという罪悪感を抱えながら働く同僚ママ看護師の悩みも耳にします。
常に時間に追われている
仕事中は保育園のお迎えに間に合うかどうか気がかりで、帰宅後は夕食の準備や入浴、寝かしつけと常に時間との勝負です。無事寝かしつけたあとも残った家事に追われ、自分の時間が取れず心身ともに疲弊してしまうこともあります。
子育てと仕事を両立するポイント


子育てと仕事を両立するには、家族の協力が不可欠です。パートナーや祖父母など、家族の協力を得ることで、仕事との両立がぐっと現実的になります。また、職場には可能な限り勤務調整を相談することで、心身の負担を軽減し、安定した働き方が実現できるでしょう。



高瀬 あやさん
筆者や周囲のママ看護師が両立のために実践しているポイントをお伝えします。
家族の協力を得る
「朝の保育園送迎は夫、夜の寝かしつけは私」など、家庭内での役割を話し合って決めることで、無理なく日々を回しやすくなります。
祖父母が近くに住んでいる場合は、保育園の送迎や急な呼び出し時の対応など、助けを借りましょう。いざというときに夫婦以外に頼れる相手がいるというのは、それだけで安心感が増します。
また、勤務変更やこどもの成長に合わせて、家族との連携もアップデートが必要です。



高瀬 あやさん
月1回の家族の予定や役割分担を確認する「家庭ミーティング」を設けている家庭もあります。
可能な限り勤務を調整してもらう
職場との連携も、仕事と育児の両立には欠かせない要素です。一歩踏み出して、周囲に協力を求めましょう。
家族のスケジュールに合わせてシフトの希望を伝えることも大切です。



高瀬 あやさん
保育園行事の日や夫が出張でワンオペになる日など、シフトの調整が必要な日を事前に伝えておくと、職場も配慮しやすくなります。
職場で利用できる子育て支援制度


職場で利用できる子育て支援制度には、育児短時間勤務や夜勤免除、子の看護休暇などがあります。看護師として働くママにとって、職場の子育て支援制度は心強い味方です。



高瀬 あやさん
制度を知っているかどうかで、働きやすさが大きく変わってきます。
ここでは、未就学児を養育する看護師が職場で利用できる、おもな子育て支援制度を紹介します。
短時間勤務制度
短時間勤務制度は、3歳未満の子を養育する労働者が、仕事と育児を両立しやすくするために設けられた制度です。[2]事業主は、1日の所定労働時間を原則6時間に短縮する措置を講じる義務があります。[3]
深夜業(夜勤)の制限
育児や介護を理由に、午後10時〜午前5時の深夜時間帯の勤務を制限できる制度です。[2]育児・介護休業法に基づき、対象労働者が申請することで、事業主は原則として深夜勤務を命じられなくなります。[2]
所定外労働の制限(残業免除)
所定労働時間を超える残業(所定外労働)を免除する制度です。小学校就学前の子を育児中の労働者が申請することで、事業主は原則として残業を命じられません。[2]
時間外労働の制限(残業制限)
法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働について、上限を設ける制度です。[4]育児中の労働者が申請することで、月24時間・年150時間を超える残業を禁止できます。[2]
子の看護休暇
こどもが病気やけがをした際に取得できる休暇制度で、年間最大5日(2人以上のこどもがいる場合は10日)まで取得可能です。[2]



高瀬 あやさん
2025年4月の改正により、これまで小学校就学前だった対象が小学校3年生までに拡大されました。[5]
この改正により、インフルエンザなどの感染症による学級閉鎖や出席停止、入園・卒園・入学式への参加などでの利用も可能になります。[5]こどもの行事で利用できるのは嬉しいですよね。
ママ看護師の働き方3つの例


夜勤が難しいママ看護師には、日勤のみの勤務や夜勤免除制度を活用する働き方があります。シフト調整が可能かどうか自身の職場に確認してみるのも一つの方法です。



高瀬 あやさん
ここでは実際に筆者の周囲のママ看護師の働き方として、日勤のみ、日勤+夜勤、訪問看護の3例をご紹介します。
| 働き方 | 勤務時間・仕事内容 | 働き方の特徴 |
| 1.日勤のみ | ・総合病院の外来勤務・9時00分~16時15分までの時短勤務 | ・夜勤がなく、保育園の送迎に間に合う・休日はこどもとの時間を過ごせる・カレンダーどおりの勤務のため、先の予定が立てやすい |
| 2.日勤+夜勤 | ・総合病院の病棟勤務・9時30分~16時15分までの時短勤務 | ・夜勤は、家族と相談して勤務可能日の調整が可能・平日の休みがあるため、自分の時間を確保できる |
| 3.訪問看護 | ・施設や病院ではなく、利用者の自宅を訪問してケアを行うスタイル・8時30分~17時00分までのフルタイム勤務 | ・勤務時間が比較的自由で、日勤中心・急なこどもの体調不良にも対応しやすい・夜勤がなく、保育園の送迎にも間に合う |
両立のコツは「がんばりすぎない」こと


制度を利用して働き方を変えたり、家族や外部のサービスを利用したりすると育児との両立は可能です。ただ、「母親だから」「看護師だから」と完璧を求めすぎると、心も体も疲れてしまいます。



高瀬 あやさん
できないことは無理に抱え込まず、家族や職場に頼る勇気を持ちましょう。
自分のペースを大切にして、少しでも休める時間を確保すると、長く安定して働き続ける力になります。子育ても仕事も「できる範囲で」「助けを借りながら」進めることが、長く続けるための秘訣です。
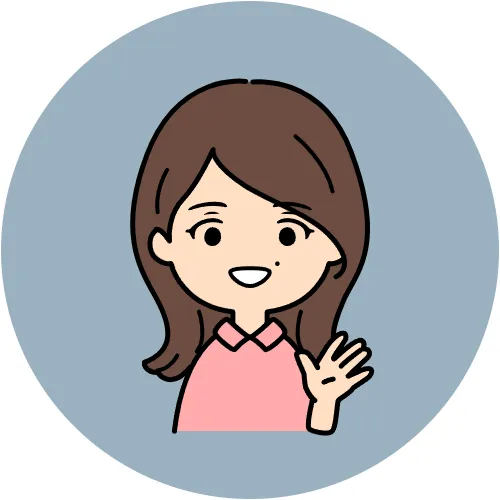
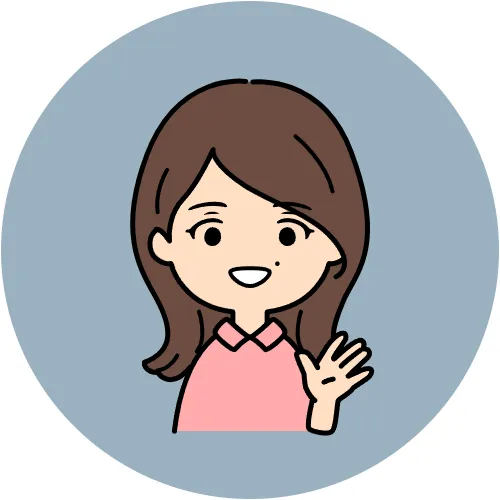
看護師ライター:高瀬 あやさん
看護師歴10年。幅広い疾患や多くの患者さんと関わってきた経験を活かし、疾患や看護についての記事を執筆。現在も総合病院で働きながら、1児の子育て中でこどもの怪我や疾患についても発信。「読者の悩みや不安解決の一助となる」ことを大切に執筆活動をしています。
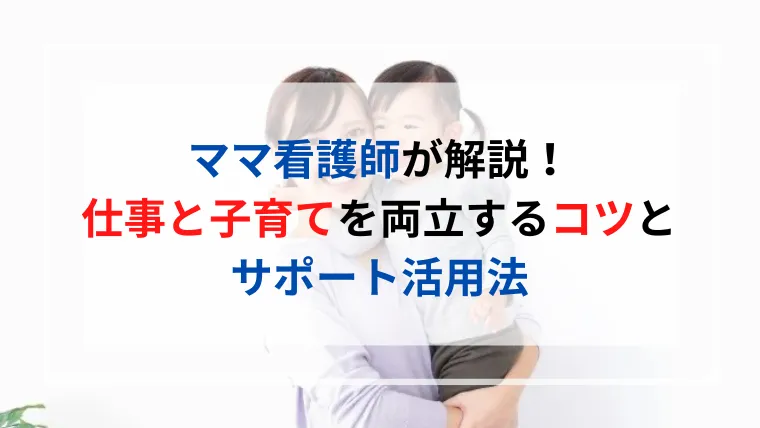
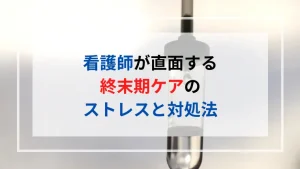
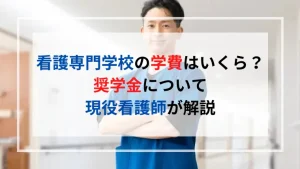
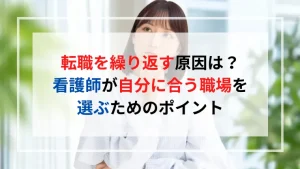
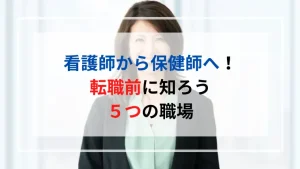
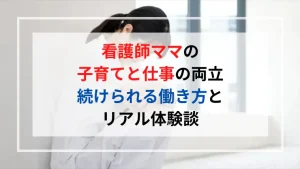
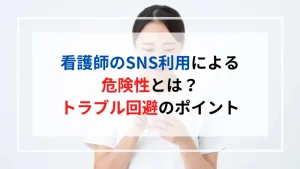
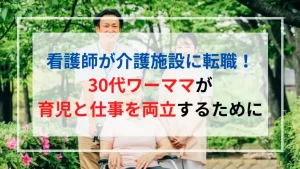
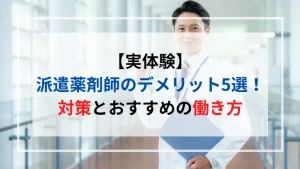
コメント